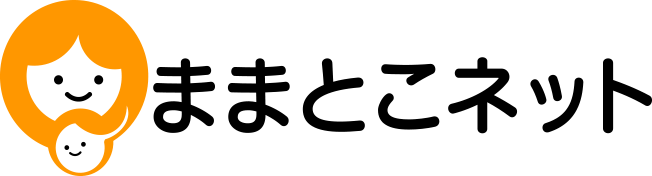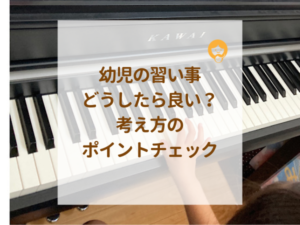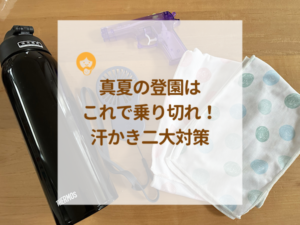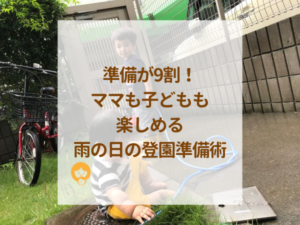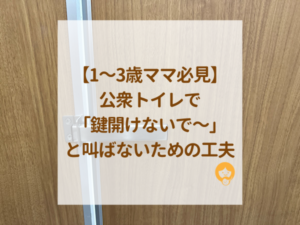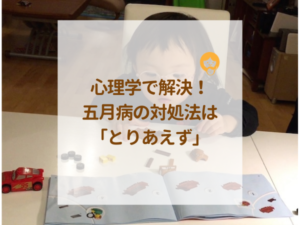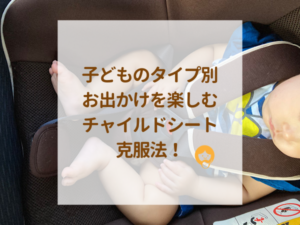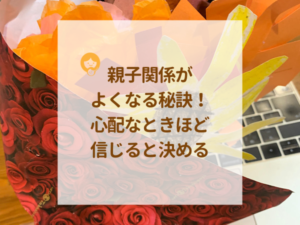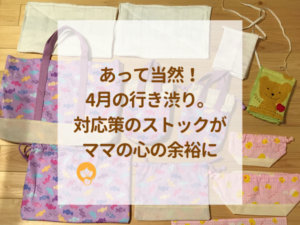ゆみ/ライター
ゆみ/ライター9月になると、また新生活が始まりますね。新しい環境が楽しい子がいれば、慣れるのに時間がかかる子もいます。新しい環境に適した振る舞いができるようになるのは、何歳ごろからでしょう?
国によってこんなにも違う!気持ちが伝わる挨拶の方法は?
新しい学期が始まると、環境だけでなく、お友達も変わることがありますね。新しいお友達と仲良くするのに欠かせないのが挨拶です。お子さんはじょうずに挨拶できますか?
挨拶の方法は、国によって全然違います。私が住んでいたハンガリーでは、お互いのほっぺたをくっつけてチュッチュッとします。初めに左頬、次に右頬。こんな挨拶、初めてだとびっくりしちゃいますね。
お辞儀をするのも、ほっぺたをくっつけるのも、どちらも”正しい’挨拶の仕方です。しかし、場合によっては相手を驚かせてしまったり、仲良くしたい気持ちが伝わらないこともあります。その場に適した対応ができるようになるのは、脳の発達から考えると5歳ごろからだと言われています。


初めてのご挨拶は大人の真似から始まる。臨機応変は5歳から。
日本では、幼稚園などに入園すると「ごあいさつの仕方」としてお辞儀をする挨拶を教わる子が多いと思います。“ルール”として教えることで、みんなが同じようにできるようになります。恥ずかしくてなかなか挨拶ができない子でも、方法が決まっていることで「こうすればいいんだ!」と気持ちが楽になるかもしれません。
4歳ごろまでは「教室の入り口に来たら、大きな声で挨拶をする」のように、ルールとして挨拶をしている子がほとんどです。ところが5歳ごろになると「今は他の人とお話ししてるから挨拶はあとにしよう」のように配慮ができるようになります。
5歳は“共感脳”という思いやりの気持ちが育つ時期です。相手の気持ちを考えて行動できるようになるのです。
見出し3(H2:30文字前後)
どうして挨拶するの?理由がわかれば一番いい方法を選べる
ハンガリーで生まれ育ったうちの娘は「ご挨拶してね」と言うと、相手が日本人であってもほっぺたをくっつけにいっていました。小さい頃からずっと親がそうしているのを見ていたので、それが当たり前になっているようでした。
ある時、日本から来たばかりのご家族に会う機会があり「挨拶はお辞儀をしてね。ハグするとおどろかせちゃうよ」と娘に事前に伝えました。すると娘は「わかってるよ。コロナやしな!」と自信満々に返事しました。「いや、ソーシャルディスタンスの話と違うねんけど」
ところが大きくなるにつれて、娘は2種類の挨拶を使い分けるようになったのです。日本人ファミリーに対してはお辞儀をして「こんにちは」と言うようになりました。面白いことに、ハンガリー在住の日本人ハーフの子にはハンガリー式。ポーランドの友人を訪ねたときにはポーランド式。日本語を話せるハンガリー人には日本式などなど、相手の文化や共通言語を考慮して挨拶を変えられるようにまでなったのです。これには親の私も驚きました。
ごっこ遊びを通して、思いやりの気持ちを育もう。
挨拶の目的を一つ挙げるとしたら、相手との距離を縮めることでしょうか。「あなたと仲良くなりたいです。」「あなたのことを気にかけています」というメッセージが込められているとすれば、自分の気持ちを押し付けるだけではいけませんね。
相手が今どんな気持ちでいるのかを想像することが思いやりの一歩です。かけっこで転んだ子を応援するのも、泣いている子をよしよししてあげるのも、自分が同じ経験をしたことがあるからこそ、相手の気持ちがわかるのです。
思いやりの気持ちは「優しくしなさい!」と叱ることでは育ちません。うれしいこと、ありがたいことだけでなく、悔しいことや悲しいことを経験することでも思いやりの気持ちは育ちます。絵本を読んで登場人物の気持ちを想像したり、ごっこ遊びで役になりきったりすることで様々な気持ちを理解できるようになります。
正直めんどうなごっこ遊びですが、思いやりを育む効果があるとわかると、めんどうさが和らぎませんか?今日は子どもに「お母さん役」をやってもらいましょう。お母さんの大変さも想像できるようになるかもしれませんよ。



このコラムを書いていて思いつきました!週末は家族4人で役割をシャッフルしておままごとをしてみます。そう、お母さん役はお父さんにやってもらいます!脱ぎっぱなしの靴下、裏返しのシャツ・・・